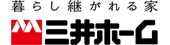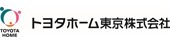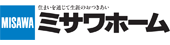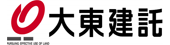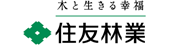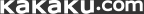長期入居を獲得するには入居者満足度の向上が不可欠。
管理会社とタッグを組んで取り組みましょう。
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
長期入居は安定した賃貸経営につながる
なぜなら、退去の手続きやホームクリーニングなど、新しい入居者を迎え入れる準備期間(1~3か月)が必要だからです。もちろん、その間の家賃収入はありません。そのため、更新ごとに退去する入居者が多いと、慌ただしいうえに収入や広告費などのロスも多くなると言えます。
退去の時期が賃貸ニーズの高い時期であれば、次の入居者を見つけるまでの期間もさほどかからない可能性がありますが、賃貸ニーズの低い時期であれば、空室が長期に渡ってしまう可能性も考えられます。
そのため、できる限り長期に渡り住んでもらえる入居者というのは、安定した賃貸経営を行うために大切な存在と言えます。
賃貸物件の平均居住期間はどれくらい?
| 世帯 | 平均居住期間のボリュームゾーン |
|---|---|
| 学生・単身世帯 | 2~4年 |
| ファミリー世帯 | 4~6年 |
| 高齢世帯 | 6年以上 |
そして、平均居住期間を算出して、一般的な居住期間と照らし合わせて、現状を把握してみましょう。
長期入居に繋げるためにはじめにすべきこと
もちろん、進学期間の終了、転勤、結婚など、やむをえない理由で退去するケースもあります。問題は「物件に不満があるから退去をする」という入居者をいかにして生まないかというところにあります。
長期に渡り住んでもらうためには、まず現状把握が先決です。そのうえで、基本的な空室対策を行いましょう。また、入居者ニーズは入居者に聞いてみるのが早道。たとえば入退去者アンケートなどで意見を収集し、空室対策に生かすのも一案です。
家賃調査
競合調査
どのような設備やサービスに人気があるかについては、入退去者アンケートや日ごろお世話になっている不動産会社や管理会社から意見収集をしてみるとよいでしょう。
入居者アンケート
また、定期的に入居者に向けてもアンケートを行い、現在の物件に対する問題を意見収集するのもよいでしょう。表面化していない不満への対策を講じれば、退去者を防ぐことにもつながります。
退去者アンケート
このように、さまざまな現状把握の方法がありますが、収集した情報を踏まえた空室対策を講じなければ、対策のピントがずれてしまう可能性もあります。入居者に長く住んでもらうためには、まず現状把握が大切なのです。
入居者のタイミング別の空室対策アイデア
既存入居者へのアプローチ方法
住みやすい環境を整える
それによって、入居者に安心感を与えることにもつながります。また、入居者としても、設備の不具合や入居者間トラブルなどの不満を伝えやすくなります。設備のメンテナンスや入居者間トラブルの解消などに速やかに対応すれば、入居者の安心感はさらに向上するでしょう。
更新タイミングの前に入居者アンケートをとる
長期入居特典を付ける
設備を拡充する
入居検討者へのアプローチ方法
フリーレントの設定
フリーレントの物件の賃貸借契約では、所定の期間より短い期間で退去した場合には解約違約金の支払義務を課す特約条項を盛り込むのが一般的です。契約書の吟味は必要ですが、フリーレント物件にすることで、1か月程度の家賃を無料にする代わりに、長期入居につながりやすいと言えます。
長期契約の設定
条件の緩和
そして、ペット可の物件数は少ないため、長期入居につながりやすくなると言えます。もちろん、敷金の見直し、ペットの鳴き声、臭いなどによる入居者間トラブル、既存入居者の許諾など、条件緩和の前に考えておかなければならない点は多々ありますが、検討の余地はあるでしょう。
そのほかにも2人入居を認めたり、セーフティネット住宅としたり、外国人や高齢者の受け入れをしたりなど、条件緩和の選択肢はさまざまです。
いずれのケースも費用対効果を見定めてから判断することが大切
繰り返しになりますが、まず行う必要があるのは、現状把握です。物件の強みや競合物件の状況、そして入居者の意見を把握したうえで、どの方法が効果的であるか、検討されるとよいでしょう。また、ご紹介した方法の中には、契約内容の見直しや、既存入居者への説明などが必要になることもありますので、留意しておきましょう。
まとめ
大家さんには、賃貸経営者として入居者満足を高めて、経営を安定させる務めがあります。その大家さんニーズに親身に応えてくれる取引先を見付けるのも、経営者としての大家さんの役割です。
長期入居の対策検討を、管理会社との付き合い方を再考するきっかけにしてみるのもいいかもしれません。
長期入居を獲得するには入居者満足度の向上が不可欠。
管理会社とタッグを組んで取り組みましょう。
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者

AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。