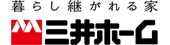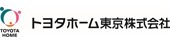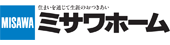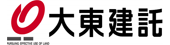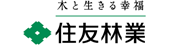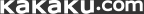退去者アンケートから入居者の声を聞いて
空室対策につなげていきましょう
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
空室対策として大家さんができること
家賃などの条件変更は簡単に行えますが、家賃を値下げすればもちろん収入も下がってしまいますし、ローンの支払いとの兼ね合いもあるでしょう。また、設備の追加やリフォームの場合は入居者のニーズや費用対効果を考えて行わないと、費用をかけても空室が埋まらないということになりかねません。
入居者の声を聞くということ
そこで今回は、入居者の声を聞くための「退去者アンケート」についてご紹介します。賃貸経営をしている大家さんは、ぜひ参考にしてみてください。
退去者アンケートの目的
退去者が出ると退去後のクリーニングや入居者募集などの手間やお金がかかりますから、入居者にはなるべく長く住んでいただきたいですよね。退去者アンケートを行うことにより、入居者の潜在的な不満や改善点を知ることができるため、空室対策や賃貸管理の対応に活かすことができるのです。
空室対策に退去者アンケートが有効な理由
1.退去理由がわかる
2.入居者の声が聞ける
「壁紙が気に入っている」「トイレの上に棚をつけてほしい」など、大家さんの視点では気付かなかった物件の特徴や入居者の要望を知ることができるのです。
3.空室対策のヒントが見える
学生の場合は入学・卒業の時期が決まっているため、入退去の時期が2月・3月に集中します。退去予定の人には早めに申告してもらい、早い客付けを狙う工夫が必要です。また、「設備の不具合」という退去理由が多いのであれば、修繕やリフォームなどを検討する必要があるでしょう。
このように、入居者からの声を聞くことにより、どのような空室対策が効果的なのかということに役立たせることができるのです。
4.設備の更新やリフォームの検討に繋がる
5.トレンドを知ることができる
退去者アンケートの内容
退去者アンケートのフォーマット
例えば、
このように、チェック方式と記述式の両方を取り入れて、入居者の負担にならずに大家さんの知りたい情報を得るフォーマットを作成すると良いでしょう。アンケートの回数を重ね、入居者とのやり取りの中で改善していくことをおすすめします。
退去者アンケートを依頼するタイミング
しかし、前者はアンケートを記載するスペースが限られてしまう点、後者は管理会社に見られながら書くことになる、退去立会に時間がかかる点がデメリットとして挙げられます。アンケートを行うには管理会社の協力が必要ですから、依頼している管理会社と運用方法について相談してみましょう。
退去者アンケートの回収率をアップする工夫
また、先ほど解説したような「解約通知書とアンケートをセットにする」「退去立会時にアンケートを回収する」という方法も回収率を高める一案として考えられます。まずは退去者アンケートを行ってみて、回収率が悪い場合は対策を検討していきましょう。
退去者アンケートを空室対策に繋げるには
など、アンケートで得た情報をまずは整理していきましょう。そこから入居者のニーズと物件への不満を分析し、設備の追加や家賃の値下げなどの対策を考えることが大切です。
定期的な入居者アンケートも有効!?
ただし、アンケートを行うことで表に出てこなかった入居者の不満を呼び起こすことになり、新たなクレームに発展してしまうかもしれません。そういった点も踏まえ、入居者から指摘された箇所で修繕が必要なものは直したり、入居者の要望のうち可能なものは取り入れたりするなど、管理会社と相談しながら入居者の不満対策をうまく考えていく必要があるでしょう。
定期的なアンケートの他、オーナーチェンジで中古物件を購入した後、既存入居者にアンケートを行うという方法も考えられます。また、入居者へのアンケートだけでなく、案内を行った客付け業者に対してアンケートを行うという方法も考えられます。
案内に行った業者はお部屋探しをしている人と一緒に内見をしているので、「決め手は何だったのか」「なぜ候補から外れたのか」という顧客の視点や、案内をした業者から見た視点を探ることができるからです。いずれにせよ、アンケートを行うには管理会社の協力が必要ですので、委託している管理会社と相談しましょう。
まとめ
また、退去者から得た退去理由・物件の不満や要望などの情報は、空室対策や今後の賃貸管理の分析に役立つことにつなげることができます。空室対策の方法は多々ありますので、気になる大家さんはぜひ、退去者アンケートを検討してみてください。
退去者アンケートから入居者の声を聞いて
空室対策につなげていきましょう
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者

宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/2級FP技能士
大学卒業後、不動産会社や住宅メーカーの不動産部に勤務し、不動産賃貸・売買契約の他、社宅代行、宅地造成などの業務に携わる。現在は、不動産や金融関係の執筆をするWebライターとして大手メディアなどに多数寄稿。初心者にもわかりやすい言葉で解説している。