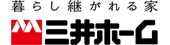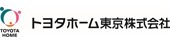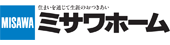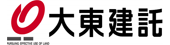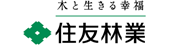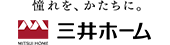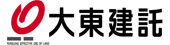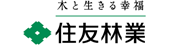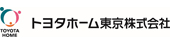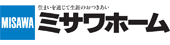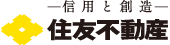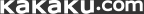所有物件が事故物件になってしまったら…
大家さんとしてとるべき対処方法や手順をおさえておきましょう!
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
所有物件が事故物件になる可能性はゼロではない
厚労省のデータによると、平成30年の自殺者数は2万840人で、自殺した場所は「自宅」が59.2%と圧倒的に高い結果となっています。自殺以外にも、所有物件で殺人事件が起こってしまう可能性もあるでしょう。
ちなみに、警察庁のデータによると令和2年の殺人事件の件数は929件となっています。
事故物件とは
とはいえ、とくに3つ目の自然死の場合まで事故物件と考えるべきかというと難しい問題になります。最終的に、事故物件かどうかは、住む人が「もしそのことを知っていたら住まなかった」という場合に、損害賠償できる心理的瑕疵に該当するかどうかで判断されると考えるとよいでしょう。
自然死については半年以上経過した場合には告知義務はないとする判例もあります。
所有物件が事故物件になった際の対処法
1. 警察と保証人や相続人に連絡
2. 賃貸契約の解約手続きを行う
3. 損害賠償について遺族と話し合い
4. 室内清掃を行う
また、事故物件となってしまったことにより物件価値が下がってしまうことも珍しくありません。その場合は、空室対策を目的として付加価値を加えるようなリフォームを検討してもよいでしょう。
供養(お祓い)を行うこともある
5. 客付けを開始する
既存入居者への対応も忘れずに
自分が住んでいる部屋でなくとも、同じ建物内で亡くなった方がいることを気にする方もいらっしゃいます。なお、中には賃下げ交渉や退去費用を請求されることもあるかもしれませんが、基本的には対応する必要はありません。
所有物件が事故物件になった時にかかる費用
| 残置物処理 | 5,000~15,000円/m2 | |
|---|---|---|
| 室内清掃(特殊清掃) | クロス張替え | 1,000~2,000円/m2 |
| フローリング張替え | 3,000~4,000円/m2 | |
| 畳の交換 | 8,000~12,000円/畳 | |
| 間取り | 費用相場 |
|---|---|
| 1R・1K・1LDK | 10~30万円 |
| 2DK・2LDK | 15~50万円 |
| 3DK・3LDK | 20~70万円 |
| 4DK・4LDK | 25~90万円 |
孤独死保険を検討しよう
孤独死保険とは、所有物件内で発生した入居者の死亡事故で生じた「遺品整理費用」や「原状回復費用」、事故後の「家賃損失」について補償を受けられる保険です。
補償内容や補償額は、利用する商品や契約内容によって異なりますが、おおむね原状回復費用で100~200万円程度、家賃損失費用について100~200万円程度(それぞれ負担した額を上限とするのが一般的)といった形になっていることが多いようです。
また、家賃損失については家賃補償保険に加入することで保証を受けることもできます。家賃補償保険は大家さん向けの保険で、孤独死に限らず入居者の死亡や火災や落雷などの災害などで家賃損失が生じた場合に補償を受けられるものです。
災害などにより家賃を受け取れなくなった場合に、その期間分の家賃(最大6か月など上限あり)の補償を受けられるほか、入居者が亡くなっているケースでは孤独死保険と同様、原状回復費用の補償を受けられます。
事故物件の客付けはどのように行えばいい?
家賃を下げる
初期費用を下げる
リフォームする
たとえば、最近では賃貸住宅でも壁付けキッチンではなく対面キッチンが好まれる傾向にありますが、古い賃貸物件でもこうしたニーズにマッチしたリフォームを実施することで空室対策とするのです。
大掛かりなリフォームとなると大きな費用がかかってしまうため、空室対策として有効なのか、長期的に見て家賃や初期費用を下げるのとどちらがより効果的なのか、慎重に判断することをおすすめします。
建て替えをすれば、より入居者の心理的瑕疵が下がります。
さらに、ハウスメーカーによるデザイン性の高い物件に建て替えることで、空き室対策に繋がることも。事故物件による建て替えを検討している方は、まずはプラン一括請求をしてみましょう。
ただし、事故物件を建て替えても、資産価値は変わらず告知義務も同じように課せられる点には注意が必要です。
土地活用プラン一括請求はこちら 無料
安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
告知義務
とくに、自然死の場合は半年ほど経過した後は告知しなくてもよいといった判例があることもあり、半年待ってから客付けを行うことも1つの方法です。
まとめ
いざ事故物件になってしまったら、残置物処理や清掃などお金のかかる手続きが必要なのに加え、事故後の客付けが難しくなるのが一般的です。
所有物件が事故物件になってしまったら…
大家さんとしてとるべき対処方法や手順をおさえておきましょう!
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者

AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。