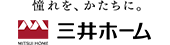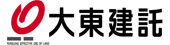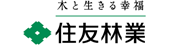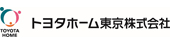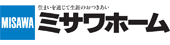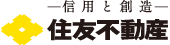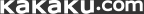- 大家さんと入居者の間で結ぶ賃貸借契約の基礎知識を把握しておきましょう。
- 普通借家契約と定期借家契約の2種類の違い、契約書の内容を把握しておくことがトラブル回避のポイントです。
- 今後の法改正に合わせてアップできるよう、常にアンテナを張っておくとよいでしょう。
土地活用プラン一括請求はこちら 無料
安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
賃貸借契約とは
借主決定~契約完了までの流れ
1.不動産会社に仲介を依頼する
2.不動産会社が入居者を見つけ申込を受ける
3.入居審査
4.宅建士による賃貸に関する重要事項説明
5.賃貸借契約の締結
基本的に、不動産会社に仲介を依頼した後は、その手続きのほぼすべてを不動産会社が行うことになります。
契約方法は「普通借家契約」「定期借家契約」の2種類
以下、「普通借家契約」と「定期借家契約」の違いや「転貸借契約」について確認していきましょう。
「普通借家契約」「定期借家契約」の違い
| 定期借家契約 | 普通借家契約 | ||
|---|---|---|---|
| 契約方法 | 公正証書 | 口頭でも可 | |
| 契約更新 | 基本的になし | あり | |
| 契約期限 | 自由 | 1年以上 | |
| 中途解約 | 借主 | やむをえない場合可能 | 可能 |
| 貸主 | - | 正当事由が必要 | |
普通借家契約は契約期間を1年以上で定める必要があり、正当事由がない限り更新が継続され、借主からの中途解約は可能である一方、貸主からの中途解約には正当事由が可能など、借主の権限の強い契約となっています。
定期借家契約は最初に定めた期間が終了すれば更新されず、原則として借主からの中途解約の申出ができないなど、貸主の権限の強い契約です。ただし、再契約で更新することも可能なため、たとえば2年の定期借家契約を締結し、優良な入居者であれば再契約するという方法も考えられます。
もし数年後に子や親族が使う予定が決まっている、転勤の期間だけ賃貸に出したいなど賃貸として利用できる期間が限られている場合や近隣トラブルを起こした場合入居者を契約満期で退去させたいなど心配に感じられる場合は定期借家契約を選択するとよいでしょう。
なお、普通借家契約の途中から定期借家契約に変更することも可能ですが、借主の合意がないと変更ができないためトラブルにならないよう、借主の入退去のタイミングで行うことをおすすめします。
業者が間に入る転貸借契約という種類も
転貸借契約のメリットとしては、大家さんはサブリース会社から賃料を受け取るため、空室状況によらず毎月一定の賃料を受け取れるという点が挙げられます。
一方、デメリットとしては、自分で賃貸経営して満室時の賃料を受け取るのと比べると賃料が安くなってしまう点や、経営状況がうまくいかない時には、転貸借契約が打ち切られてしまう可能性があるといったことが挙げられます。
サブリースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
賃貸借契約書とは
賃貸借契約書では、借主が物件に入居する代わりに、貸主に対して賃料を支払う旨や、入居の時期、賃料の額などが書かれている他、賃料が支払われない場合のペナルティなどについて書かれています。
いざ何らかのトラブルが起こったときには、賃貸借契約書に記載の内容で判断されるため、どんな内容で契約するのかしっかり確認しておくことが大切です。
賃貸借契約書のチェックポイント
ちなみに、契約書は一般的に不動産会社が作成してくれますが、入居者との間で賃貸借契約を結ぶ際に大家さんは立ち会わない場合も多いです。事前にどんな内容の賃貸借契約書を作成しているのか見せてもらえるように話をしておくとより安心できるでしょう。
賃貸借契約書には何が書かれているか?
1.家賃滞納
一般的には、「〇か月以上家賃を滞納したときは催告なしに契約を解除できる」などと記載されていることが多いです。また、上記期間に該当しない場合でも、複数回にわたり家賃を滞納している場合には「信頼関係を損なった」として、契約を解除できると記載することもあります。
なお、入居者が家賃を滞納したとき、大家さんは家賃の入金について催告をし、それでも入金のない場合に契約を解除できることとされていますが、賃貸借契約書に「無催告解除特約」を設けることもできます。
2.中途解約・契約解除・違約金
賃貸借契約では、契約期間を2年とすることが多く、この期間より前に解約するものは中途解約となり、違反金が発生する可能性があります。とはいえ、借主からの解約については、契約しやすいよう、期間途中でも解約しやすいよう解約についての特約が設けられているのが一般的です。
ただし、上記はあくまでも一般的な話であり、契約書によっては「入居から半年以内に退去する場合賃料1か月分の違約金を支払う」など、中途解約に違約金が発生する旨の記載があることもあります。また、フリーレント契約の場合、「入居から2年以内に退去する場合は賃料1か月分の賃料を支払う」など、より厳しい内容にすることがあります。
3.特約事項
敷金と原状回復
特約の内容が、ガイドラインの内容を超えて借主に負担を課すものとなっている場合、内容によっては無効となることがあります。
使用・利用の禁止
・廊下・階段などの共用部に物品を置くこと
・居室内にピアノや楽器を持ち込み演奏すること
・火事の原因になり得る石油ストーブの使用やタバコ
・ペットの飼育
・1人用の住居に複数人での入居
・住居専用の物件での事務所やSOHOとしての利用
・転貸借
4.契約後の変更
契約書の内容変更をしたい
賃料を上げたい
2020年の民法改正に伴い、契約書にいれるべきこと
1.敷金に関する条項(新法621条)
2.一部滅失により賃料減額請求しなくても賃料が減額される(新法611条)
3.保証金の限度額を設定する(新法465条の2)
今回の改正民法は大幅な改正ですが賃貸借契約についてはそこまで大きな影響はありません。しかし、今後も定期的に法改正される可能性があります。契約書の内容にも影響が出る可能性があるため、賃貸経営に関する情報のアンテナを常に張っておきましょう。
まとめ
賃貸借契約書の内容について、本記事を参考に少なくとも重要な部分については自分でチェックできるようにしておき、不動産会社に任せきりにしないよう気を付けましょう。
賃貸経営を始めるなら不動産会社に任せきりは厳禁ですが
頼れるパートナーと経営プランを立てることから始めるのが成功のカギです。
土地活用プラン一括請求はこちら 無料
安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者

AFP/2級FP技能士/宅地建物取引士/相続管理士
明治学院大学 経済学部 国際経営学科にてマーケティングを専攻。大学在学中に2級FP技能士資格を取得。大学卒業後は地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より父親の経営する住宅会社に入社し、住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。