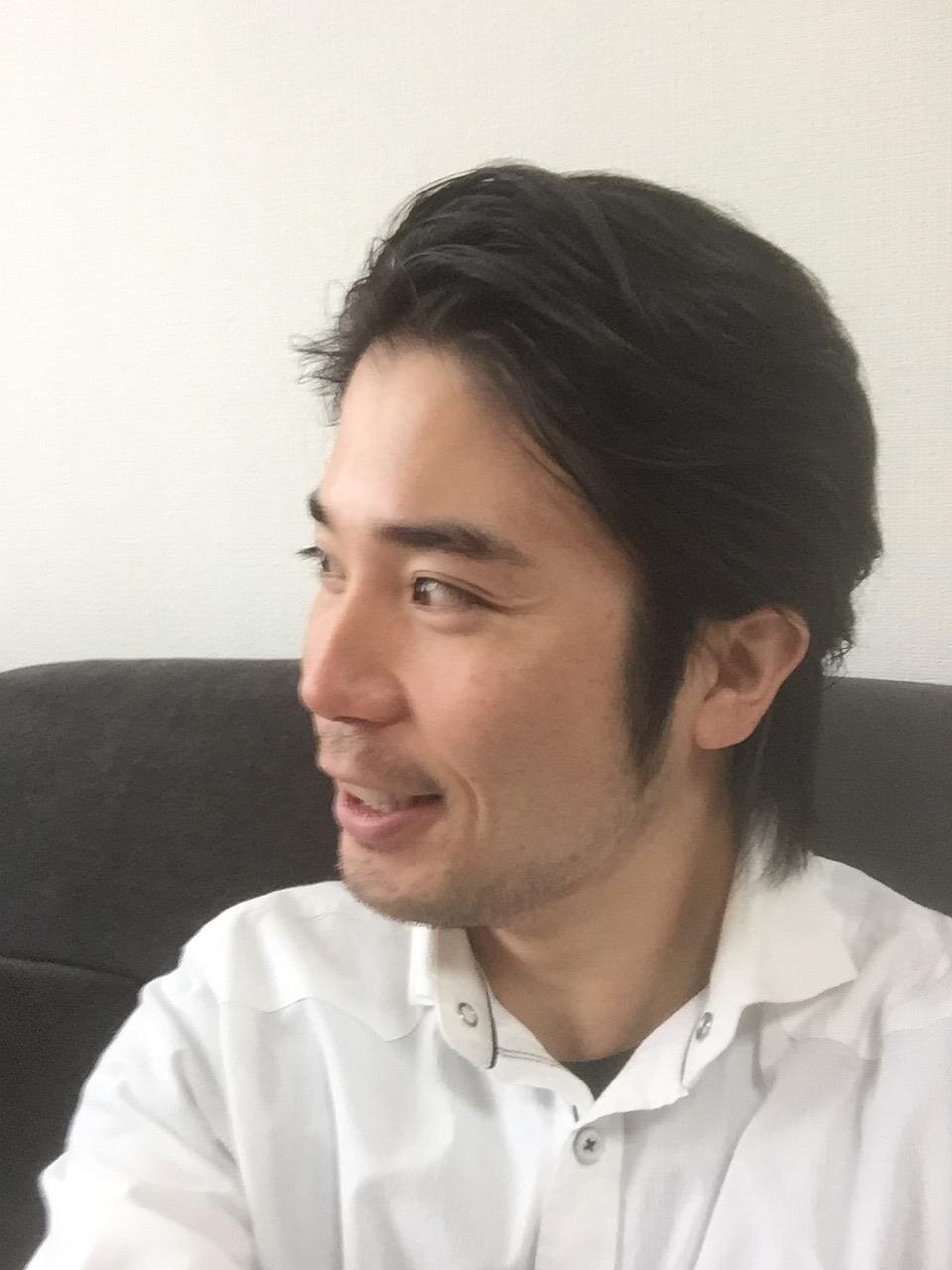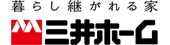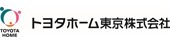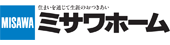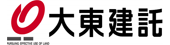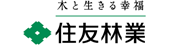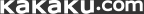高齢者の受け入れは有効な空室対策のひとつ!
プロと相談しつつ、前向きに検討してみませんか?
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
高齢者の住まい事情
このように、高齢化が進む中で、大家さんは高齢者の入居に拒否感を感じているようですが、実際、高齢者の方たちの住まい事情はどのようになっているのでしょうか。
ー生涯賃貸で暮らし続ける高齢者
持ち家に住んでいる人が圧倒的に多いものの、賃貸住宅に住んでいる高齢者は一定数存在しています。
また、下表から、ひとり暮らしの高齢者で持ち家を持つ人は少ないことがわかりますが、今後も高齢化が進んでいくこと、そして、同時に未婚率も高い水準で推移していることを加味すると、さらに高齢の単身者が増えていくと予想されます。
| 同居者 | 持ち家率 |
|---|---|
| ひとり暮らし | 65.4% |
| 夫/妻・パートナー | 90.5% |
| 親 | 93.9% |
| 子 | 92.0% |
| その他(親族以外も含む) | 77.0% |
高齢者は賃貸物件への入居が難しい?
先ほどの「高齢者の経済・生活環境に関する調査」によれば、同居者がいる場合よりもひとり暮らしの方が入居を断られるケースが多くなっています。また、どのような理由で入居を断られたかについては、「高齢のため」が61.5%となっており、最も高い割合となっていました。
一方、以下、大家さんに関する2015年のデータですが、「高齢者世帯の入居に拒否感がある賃貸人」の割合が70.2%と高く、今も昔も高齢者の賃貸物件への入居は難しいようです。
<入居を拒否している賃貸人の割合>
・単身の高齢者 8.7%
・高齢者のみの世帯 4.7%
<入居に拒否感がある賃貸人の割合>
・高齢者世帯 70.2%
大家さんが高齢者受け入れに消極的な理由
病気や事故に対する不安
また、認知症も若い世代より高齢者の方が多く、認知症を原因とする火災が起きているのも事実です。火災が起きてしまえば原状回復費用などがかかり、大家さんにとっては大きな負担となってしまうため、病気や事故に対する不安から高齢者の受け入れに消極的になってしまうのも無理はありません。
孤独死に対する不安
孤独死が起きてしまった場合、遺族や警察への連絡、クリーニングや残置物処理などの原状回復業務のほか、場合によっては、遺族や連帯保証人への原状回復費用の請求も行わなければなりません。
部屋の損失が大きい場合には、事故物件として扱われることも珍しくなく、新たな入居者確保が難しくなったり、賃料を下げざるを得なくなったりする可能性もあります。
家賃滞納に対する不安
また、年金暮らしの高齢者の場合には経済的な余裕がないことから、やはり、家賃滞納に繋がってしまう可能性があり、大家さんが不安感を抱いてしまうのも無理はありません。
高齢者を受け入れるための事前準備
連絡が取りやすい環境を整える
高齢者向けの契約書を準備する
このような特約を設けておくことで、何日も部屋の電気がついていないなど状況に違和感があった際、早急に対応することができます。また、認知症などと診断された場合や、長期入院をする場合などは賃貸契約を解除するといった内容の特約も有効です。
家賃保証会社の利用を検討する
ただし、高齢者は審査が厳しい場合があるので、その場合は、複数の家賃保証会社に依頼が必要です。
リフォームなどで設備を整える
国土交通省が舵を取る「住宅セーフティネット」を使えば、リフォームをする際に補助金をもらえる可能性もあります。検討するときは窓口に問い合わせみましょう。
事前準備で不安を減らすことができる
高齢者受け入れで享受できるメリット
長期入居が期待できる
なぜならば、高齢者は引退している方が多く転勤も転職もないため、引越す必要がありません。そのため、よほどのことがない限りは長く住み続けてくれる可能性が高く、大家さんにとってはメリットといえます。
まとめ
高齢化が進んでいる中でも、高齢者の受け入れに懸念を示す大家さんは多いものです。しかし、高齢化の世の中において、高齢者の入居は空室対策のひとつとして避けては通れないものとなるかもしれません。まずは、受け入れ体制を整えながら、はじめてみてはいかがでしょうか。
高齢者の受け入れは昨今、有効な空室対策のひとつです。
プロと相談しつつ、前向きに検討してみませんか?
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者

宅地建物取引士
新卒で不動産ディベロッパーに勤務し、用地仕入れ・営業・仲介など、不動産事業全般を経験。入居用不動産にも投資用不動産にも知見は明るい。独立後は、不動産事業としては主にマンション売却のコンサルタントに従事している。