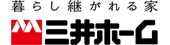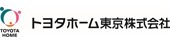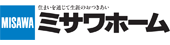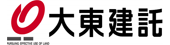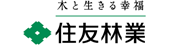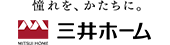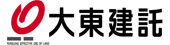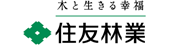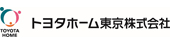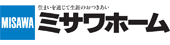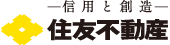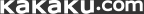賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
サブリース新法が施行!その背景とは
過去、サブリース事業を行っていたシェアハウス業者が破綻したことで多くの大家さんがトラブルに巻き込まれるという事件がありましたが、そのほかにもサブリースをめぐるトラブルはさまざまです。サブリース新法によって、トラブル発生の抑制につながることが期待されています。
おさらいしよう!「サブリース」とは
これをマスターリースといいますが、サブリース業者は、第三者に賃貸して家賃収入を得ます。もちろん、空室が生じる可能性もありますが、サブリース業者は入居者の有無を問わず、大家さんに家賃保証をします。
なお、実際に入居者が支払う家賃よりも、サブリース業者が大家さんに支払う家賃は低めに設定してあります。これは、サブリース業者が空室リスクを負ったり、入居者募集および手続き等を行ったりするコストを考慮しているからです。
実際に入居者が支払う家賃よりも少ないとはいえ、大家さんとしては空室リスクに頭を抱えることなく、安定的に家賃収入を得られるメリットがあります。
サブリースの問題点やトラブル内容
また、サブリース家賃の減額を求められるなどしたため、サブリース契約の解約を申し出たら違約金を求められるといったトラブルも少なくありません。
社会問題にまで発展したこのようなトラブルを防止するために、サブリース新法が施行されたのですが、では、このサブリース新法にはどのような規定が盛り込まれているのでしょうか。
サブリース新法の内容
2020年12月施行の「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に係る措置」においては、以下のような規定が法律に盛り込まれています。
①誇大広告の禁止
②不当な勧誘行為の禁止
③特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」にさらに詳細に記載してありますので、一読されることをおすすめします。
2021年6月には賃貸住宅管理業法が施行
1. 一定の年数以上の実務経験を持つ人材や住宅管理の有資格者の配置
2. 入居者から徴収した金銭と業者の資金・財産を分割管理
3. 契約者への定期報告
サブリース新法で何が変わる?
「賃貸住宅の管理業務などの適正化に関する法律」の施行によって、「誇大広告の禁止」、「不当な勧誘行為の禁止」、「特定賃貸借契約締結前の重要事項説明」がサブリース会社に求められることになります。
新法の施行によって、どのような変化が生じる可能性があるのか、そして、大家さんとしてどのような姿勢を持つべきなのかについて、ご説明いたします。
サブリース会社の説明責任
新法の施行に伴い、「特定賃貸借契約締結前の重要事項説明」がサブリース会社に義務付けられることになるため、悪質なサブリース会社は淘汰されることになるでしょう。
また、大家さんがサブリース契約の内容をよく理解したうえでサブリースをスタートできるようになる可能性が高いと考えます。
賃貸管理の適正化
これにより、悪質な賃貸管理業者は淘汰されることになります。
大家さんの意識改革
いくら、「特定賃貸借契約締結前の重要事項説明」がサブリース会社に義務付けられることになるとはいえ、大家さん自身が、その説明を理解しようという姿勢がなければ意味は半減します。
また、サブリースを活用するにしても、賃貸経営はその言葉どおり事業経営にほかなりません。業者の提案を鵜吞みにするのではなく、事業の収支妥当性や継続性、リスクを大家さん自身も検証してみる必要性があるでしょう。
これからサブリースを含めた賃貸経営を検討するなら
これらの方法を検討することで、より自分のニーズやライフスタイルに合った土地活用が実現できるかもしれません。
無料で土地活用プランを比較できる一括請求サービスを利用して、さまざまなプランの中から自分に最適な土地活用の方法を見つけてみてはいかがでしょうか?
土地活用プラン一括請求はこちら 無料
安心の提携企業がさまざまな土地活用プランをご提案致します

※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
よくある質問
- サブリースのデメリットとは?
- 本来の家賃を下回るサブリース賃料を受け取ることになったり、礼金収入はサブリース業者の収入になったりするため、収入の最大化ができないデメリットがあります。また、入居者募集や入退去の手続きなどはサブリース業者が行うことになるため、大家さんが自ら入居者を選ぶことはできない点もデメリットと言えるでしょう。詳しくはこちらの記事を参照ください。
- サブリース契約書内で確認すべきポイントは?
- サブリースでよくあるトラブルとして「予期せぬ賃料減額」があげられますが、実は、将来の家賃変動の条件については、サブリース契約書内に記載されている事項です。言い換えれば、大家さんが契約書を確認していれば未然に防げたトラブルとも言えます。サブリース契約締結時には「賃料減額のリスク」について必ず確認しておきましょう。詳しくはこちらの記事を参照ください。
- サブリース業者を選ぶときのポイントは?
- 賃貸経営における空室リスクを回避してくれるサブリースは、大家さんを守るための仕組みです。大家さん、そしてサブリース業者がWIN-WINの関係となるために、サブリースを活用する際には、お互いに協力しながら賃貸経営の安定的な運営を目指していけるパートナーとなるサブリース業者を選ぶことが大切です。詳しくはこちらの記事を参照ください。
まとめ
サブリースをめぐるトラブルの多くは、サブリースおよびサブリース契約についての理解不足が原因です。
新法施行により、トラブルは減少する可能性はありますが、大家さん自身の意識改革は必要不可欠です。賃貸物件を活用した事業の経営者である意識を持って賃貸経営に向き合い、空室リスク回避のための一手段としての有効性を検証してみてはいかがでしょうか。
サブリースの新たな法規制について理解を深め
あなたの賃貸経営に有効に活用しましょう!
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者

AFP/社会福祉士/宅地建物取引士/金融広報アドバイザー
日本社会事業大学 社会福祉学部にて福祉行政を学ぶ。大学在学中にAFP(ファイナンシャルプランナー)、社会福祉士を取得。大学卒業後、アメリカンファミリー保険会社での保険営業を経て、(マンションデベロッパー)にてマンション営業、マンション営業企画に携わった。その後、2008年8月より独立し、現在、自社の代表を務める。