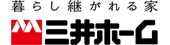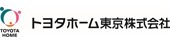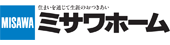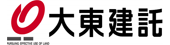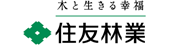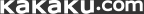相続税や贈与税などに影響する?
親子間の不動産賃貸に関わる税金についておさえておきましょう!
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
目次
賃貸物件の空室を無料で子供や親族に貸しても問題ない?
しかし、この「親族に無料で使わせる」という行為は、税金を計算する上でさまざまな箇所に影響を及ぼします。賃貸物件の空室を子供や親戚に無料で使わせても、ただちに贈与税や所得税が課されるわけではありません。
その意味では親族などへの無料貸付に大きな問題はありません。しかし、さまざまな部分に微妙に影響を及ぼすため、どこにどのような影響が及ぶのか知っておくことは助けになります。無料で空地空室を使わせることが子供のためであるとしても、注意深くあることは重要です。
使用貸借と賃貸借
引っ越しの時に友人から車を借りて、使い終わったら返す、御礼に焼肉を御馳走する。これは車の使用貸借となります。簡単に言えば、タダで貸し借りすることで、使用料を支払わない分、使用者に権利はなく保護されません。
「賃貸借」の方が耳馴染はあるのではないでしょうか。身近な例で言えば、レンタカーやレンタルDVDなどは賃貸借に該当します。「賃貸借」とは有償で貸し借りすることです。有償である分権利は強く法律で保護されます。
不動産の「使用貸借」と「賃貸借」の境界線は、固定資産税相当額です。不動産の年間使用料がその不動産の年間の固定資産税額と同額程度である場合、その不動産の貸し借りは「使用貸借」となります。つまりタダ同然という訳です。使用料が年間の固定資産税相当額を明白に超える場合、その貸し借りは「賃貸借」と判断されます。
親子間の不動産賃貸は税金に影響する
相続税
自分自身で使っている土地を「自用地」といい、人に貸している土地を「貸地」といいます。また、建物を建て人に貸している場合のその建物敷地を「貸家建付地」といいます。自用地に比し、貸地や貸家建付地の評価は低くなります。
借地人や借家人の有する権利の分、評価が差し引かれるためです。この評価減を見込んで、相続対策としてご所有の土地を貸地や貸家建付地とすることは、昔からある相続対策の1つです。
しかし、先に述べた通り、借地人や借家人の権利が保護されるのはあくまでも賃貸借が行われている場合です。使用貸借である場合、借りている人に特段の権利はありません。その土地の評価は貸地や貸家建付地とならず、自用地評価となります。相続税の減少効果を見込んで貸地や貸家建付地にしたとしても、親族に無償で貸してしまえば、その評価減の効果は失われます。
小規模宅地の特例との関係
しかし、使用貸借で親族などに貸し付けられる土地は、被相続人の居住用や事業用、貸付用の土地とは認められません。使用貸借されている土地は、借りている人の居住用や事業用として扱われるためです。
使用貸借されている土地が被相続人の小規模宅地等の適用を受けられるのは、被相続人と土地を借りている人が同一生計の親族である場合のみとなります。親族への無償の土地の提供が、相続対策、特に小規模宅地の特例の適用関係に悪影響を及ぼしていないか、検討しておくことは重要です。
贈与税
法人税の世界では、通常収受すべき家賃を貰っていないと、その分の家賃相当額は、贈与等として貸主側でも課税の対象となる場合があります。しかし、個人間においてはそのような取り扱いはありません。扶養義務者相互間での生活扶助は贈与税の対象外となります。
所得税
このため必要経費と認められない部分が出てきます。たとえば、同じ広さの4部屋のアパートを所有している人が、そのうちの一部屋を息子にタダで使わせたとします。この場合必要経費の集計にどのような影響が出るでしょうか。
まず、このアパートに係る土地建物の固定資産税のうち必要経費にできるのは4分の3となります。4分の1は自用扱いだからです。減価償却費も建物全体に係るものは同じく4分の3しか必要経費になりません。
借入金利息や共用部の電気代なども同じ取り扱いになります。息子にタダで貸すと家賃収入が減るので、不動産所得が減少し所得税が安くなる、と見込んでいても、予想に反して税負担はさほど減少しないという結果はよくあることです。
親子間の不動産賃貸における注意点
小規模宅地の特例の対象外となる可能性も否定できません。所得税では、不動産所得の金額の計算上、必要経費とできる範囲が狭まります。
子供や親戚に不動産を無償で貸し付けている方は、現状の貸付状況が、ご自身の所得税や相続税などにどのような影響を与えているか、顧問の税理士さんと見直してみることをおすすめいたします。
空室が出たら空室対策に力を入れよう
収益物件は単体で黒字の収支を出してこそ財産として価値があり、資産形成に寄与するものです。安易に子や親戚に無償提供するのではなく、空室リスクを避けるように運用することが重要です。空室が発生したら不動産管理会社などに相談するのが良いでしょう。
よくある質問
子供が親の土地を借りて家を建てたら贈与税がかかる?
それでも贈与税が課されることはありません。親子間の土地の無償の貸し借りは使用貸借として扱われます。詳しくは国税庁のページを参照ください。
子供が親の借地に家を建てたら贈与税がかかる?
それでも贈与税は課されません。この場合もこの取引は使用貸借として取り扱われます。詳しくは国税庁のページを参照ください。
子供が親名義の建物に増築したら贈与税がかかる?
子供が負担した増改築資金に相当する家屋の持分を、親から子供の名義へ移転して登記するならば、贈与税の問題は発生しません。詳しくは国税庁のページを参照ください。
まとめ
ご自身の賃貸経営の状況に照らして、現状をしっかりと把握することは重要です。顧問税理士や頼りになる不動産会社と相談し、実りの多い賃貸経営を行ってください。
相続税や贈与税などに影響する?
親子間の不動産賃貸に関わる税金についておさえておきましょう!
賃貸経営のお悩みはプロに相談!
プラン提案を受けてみませんか?
70社以上の有力管理会社が大家さんのお悩み解決をサポート
※ページ下部の「賃貸経営一括相談および土地活用プラン一括請求サービスの注意点」をご確認いただいたうえ、ご利用ください。
この記事の監修者

税理士/税理士法人シン総合会計 代表
会計事務所に勤務しつつ平成16年税理士試験に合格。税務コンサルタント会社にて金融機関をサポートする業務の中、資産税業務の経験を積む。平成22年税理士法人シン総合会計設立。主に中小企業の会計税務支援を中心に、事業承継、資産税業務にも従事。不動産会社の税務相談会相談員、金融機関のセミナー講師等に携わる。